
Q.面接試験に向けて、面接カード(エントリーシート)の準備をしようと思っています。とりあえず、自分なりに書いてみたのですが、どうもしっくりときませんし、何となくこれでよいのか心配です。書くときのコツはあるのでしょうか。
〈今回のテーマ〉
・自分自身がしっくりとくるESとは?
・エピソードの使い方とは?
《自分のことを「意識」していますか?》
前回の続きです。
前回は「2.面接官にとって、読みやすく、質問がしやすいES 」について述べました。今回は「1.自分の目で見て、自分が書いてあると認識できるES 」についてお話していこうと思います。
大学では、面接対策の指導も行っておりますが、そうは言っても、最終的に作り上げていくのは学生さんたちです。その際にどういう視点でESをチェックしてほしいかということを事前に伝えています。ひとつは前回お話しした「面接官にとって読みやすく、質問しやすいか」であり、もうひとつが「自分の目で見て、自分が書いてあるか」という視点です。
もし、今、お手元にESが置いてあったら、ぜひもう一度そのESを読んでみてください。「ああ、自分っぽいなあ」と素直に感じることができれば、そのESは自分の話が書けているでしょう。「…何だか、これ、誰でも当てはまるような」と感じた方は、面接官にも「また同じような受験生が来た。」と認識される可能性があります。
自分の目てみて誰だかわからないものは、他人から見ても他の人と区別することはできないでしょう。もちろん、大切なのはESではなく、面接そのものですので、そこで自分自身を表現できればよいのですが、ESで書いて表現できていないということは、面接で話すことでも表現できない恐れがあります。
それでは、どうすれば、自分自身がきちんと表現できるようになるか。それは「無意識」を「意識」に変えていくことです。具体例を添えて、話をしてきたいと思います。
例:長所…相手の立場に立って、物事を考えることができること。
自分の感覚ですと、5人に1人はこのように書いているでしょうか。決して、誤解してほしくないのは、これがダメだということではありません。おそらく、これを書いた人は、日頃、実際に相手の立場で考えているのでしょう。
ただし、これを書いた人に「相手の立場に立つって、そんなに難しいことは自分にはできないんだけど、どうすればそんなことができるの?」と聞くと、言葉に窮する人は多いです。多かれ少なかれ、誰もが多少は相手のことは考えます。長所として言う以上は、他の人以上にそれができるとPRしているわけで、「相手の話をよく聞く」程度では、面接官は納得してくれません。
本当に相手の立場に立って物事を考えているのであれば、その人なりの「心がけ」があるはずです。ただし、そこに「無意識」では、言葉としては表現できません。「無意識」を「意識」に直していく必要があります。
例:長所…相手に寄り添って、一緒に物事を考えることができること
例:長所…自分の考えにこだわらず、広く考えを受け入れられること
例:長所…相手とわだかまりなく、お互いの意見を言い合えること
いかがでしょうか。同じ「相手の立場に立って、物事を考える 」であっても、上の3つの印象はだいぶ異なるのではないでしょうか。自分自身の長所を深く「意識」することで、自分らしい表現もできるようになるはずです。エピソードそのものも大切ではありますが、自分自身の日頃の「心がけ」や「大切にしていること」、もう少し言えば「信念」や「価値観」について考え、それを表現できるようにしてもらいたいと思います。
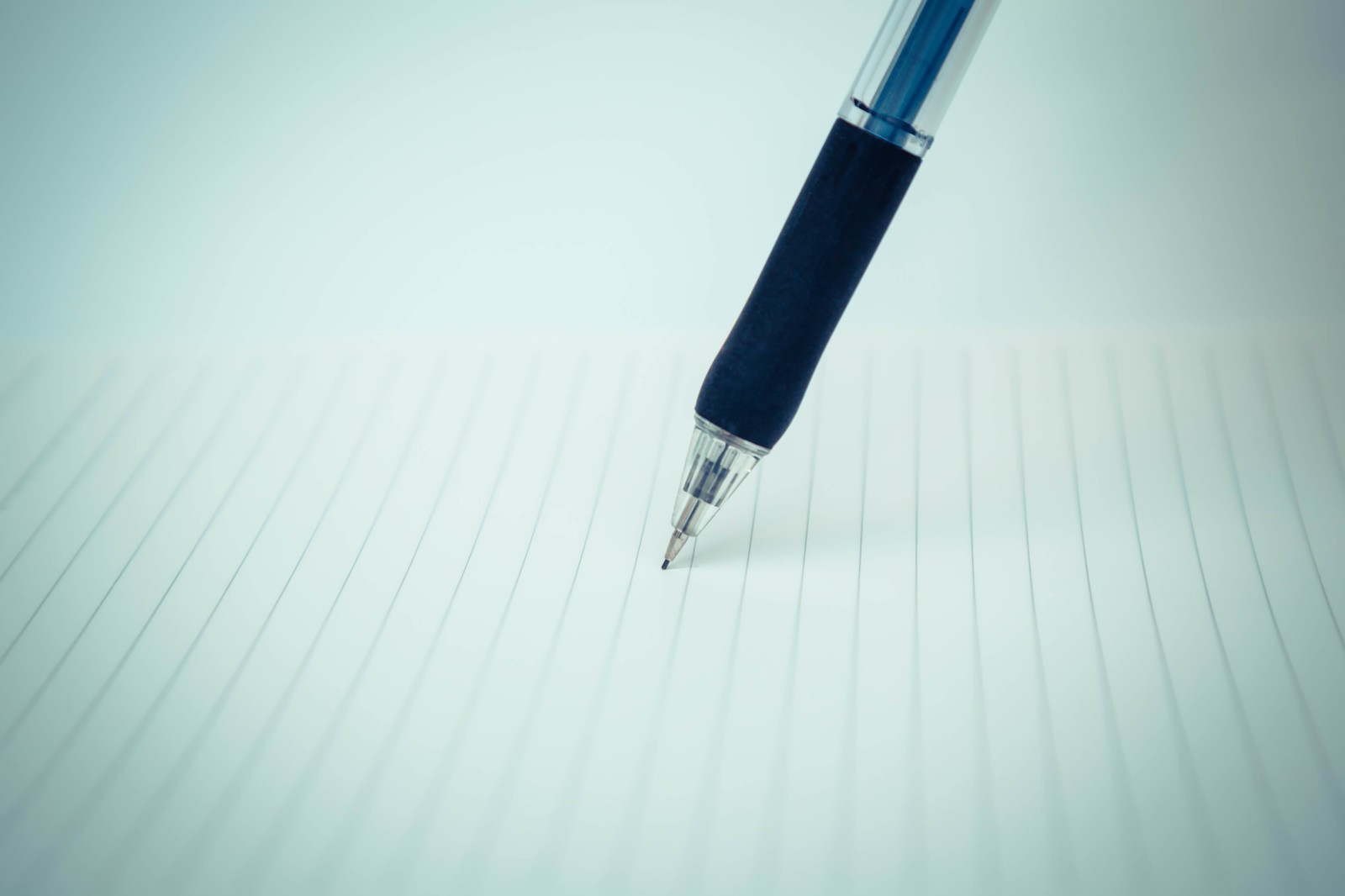
《エピソードはどこまで大切なのか?》
面接対策本の影響もあるのか、「自己分析≒エピソード」と思っている人も多いようです。ESで書かれている内容もほとんどがエピソードになってしまっているケースも多々見受けられます。
面接官は皆さんの何を見て評価をしているのかを考えてみてください。民間企業も含めた人事担当者、そして、自分自身の考えをまとめると、大きく以下の3点だと思います。
(1)一緒に働きたいかどうか
(2)ポテンシャル(将来の伸び)があるかどうか
(3)社会的常識・マナー
面接官はエピソードそのものを聞きたいわけではなく、エピソードを通して、上記の点、特に(1)と(2)をチェックしています。ESでは「具体的なエピソードを交えて、達成感や得たことについて述べてください」という内容が書いてありますが、聞きたいことのメインは「達成感や得たこと」であることを忘れないようにしてください。
ESの書き方について指導する際に、学生さんたちにお伝えするのは、自分自身の「成長(変化)」に目を向けてほしいということです。
例えば、高校入学から大学入学、大学入学から現在では、どんなふうに成長(変化)したか。社会人の方であれば、大学卒業の時点と今では、どんなふうに成長したか。これを考えてみてほしいと伝えています。
その成長した部分は何かのきっかけがあって成長したはずです。そのきっかけをひとつひとつ掘り起こしていけば、おのずからエピソードも浮かぶのではないかと思っています。
例えば、高校時代の部活を例にすると、「高校の時に部活をやっていた→そのとき自分は…」というアプローチでしっくりこない人は、「高校時代に根性付いたよな(成長)→あの部活を乗り越えたのは…」というアプローチも試みてほしいということです。
また、小学生の頃を思い起こしてみて、こういう部分はまったく変わっていないなと思うところは、その人の本質的な部分なのかもしれません。
一般的には、具体的なものは考えやすく、抽象的なものは考えにくいのでしょう。そうでれば、抽象的なものから考えはじめ、そこから具体的なものを考える、そんなプロセスもあるのではないかと思います。
自分について「無意識」では、自分を表現できません。自分を作るというよりは、過去の自分を整理して、自分の信念や価値観などを「意識」するように心がけましょう。
エピソードというほど何か特別なことでなくても、友人の一言で自分の何かが変わったり、本を読んで自分が新しい価値観を得たりすることもあります。エピソードにとらわれすぎず、自分自身を見つめてみてはいかがでしょうか。